保護者と子どもがもっと安心して暮らせるように、別府市で子ども食堂や学童保育などの「子どもの居場所づくり」に取り組んでいるのが中村さんです。
コロナ禍をきっかけに、学校や地域での過ごし方も変わり、今の時代にあった新しい形での居場所が求められる中で、保護者と子どもたちの声に耳を傾けて、様々な工夫をされています。
そこで今回は、中村さんが別府市で行っている「子育て支援の取り組み」や「子育て支援に取り組む思い」についてのインタビューをお届けします。

【中村さとる】43歳。24歳の時に美容室PADDLEを開業。わくわくキッチン子ども食堂代表。山の手小学校PTA会長。山の手キッズ第二児童クラブ代表。別府西中学校PTA副会長。別府市PTA連合会副会長。1歳6歳13歳の三女の父。子ども達の時代に素晴らしい別府市を渡すべく、福祉活動と政治活動両面から日々挑戦中。
カクシン編集部の林です!僕が聞きました!
子ども食堂、PTA会長、学童保育など幅広く「子育て支援」に取り組む

まずは、中村さんが行っている事業や活動について教えてください。
主に子どもに関わることになるのですが、私の子どもが通っている小学校のPTA会長、中学校のPTA副会長、学童保育の会長、そして「わくわくキッチン」という子ども食堂の立ち上げと代表、等に携わらせていただいています。
そんなにやられてるんですか!別府会PTA連合会ではどういったことを話し合いますか?
主に「子ども達の教育」についてですね。
例えば、コロナ禍での修学旅行をどうするかという議題で、PTA側が保護者の意見を取りまとめて報告し、PTA側と教育委員会側で意見のすり合わせをしています。
保護者の声はどのように集めているのでしょうか?
コロナ禍以前は保護者の方々と懇親会を開催して、意見交換をすることもありましたが、今はできないので、普段の会話の中から意見を集めています。
コロナ禍をきっかけに起きた「ネガティブな変化」と「ポジティブな変化」

コロナ禍になって、PTAも大変でしたか?
そうですね。
やっぱり気軽に集まれなくなったのは大変でした。
子どもたちが給食を黙食したりしているのに、大人だけ懇親会を開くわけにもいきませんしね。
なので、今は意思疎通を図るために、PTA役員メンバーでLINEグループを作って、コミュニケーションを取ったり、オンライン会議を積極的に活用したりしています。
ですが、保護者同士の懇親が取れない状況が2〜3年続いているので、改めてリアルで行う交流の大切さを実感しています。
特にお母さんたちにとって情報交換する場が大事で、そこでママ友を作り、子どもに関する悩みなどを話し合うことで、心の支えができるようです。
コロナが落ち着けば早めに動きたいと思っています。
コロナ禍になって、何か良いこともありましたか?
子どもにとって必要なことが何なのかと、ゼロベースで考えるきっかけになったのはよかったですね。
どの組織でも同じだと思いますが、PTAでも前年度に行った活動は必ず行うという習慣ができていました。
去年もやったから今年もやらないといけないと義務感で動いている感じですね。
それがコロナ禍になったことで、「これは必要?」「本当に子どもたちのためになっている?」と考えるきっかけになったのはよかったと思います。
ゼロから立ち上げた「子ども食堂」への思い

子ども食堂の活動ではどのようなことをしていますか?
子どもたちが学校から帰ってきた後に集まって、宿題をしたり、一緒にご飯を食べたりする場を提供しています。
こういった、子どもにとっての居場所は、いっぱいあったほうが良いと思うんです。
心の拠り所になりますし、様々な人と接する機会にもなります。
多ければ多い方がいいんですね?
子ども食堂は、他校の児童や違う学年の児童も集まるので、普段通っている学校にはない交流が生まれています。
また、子ども食堂にはなんの強制もありません。
参加するのに会員になる必要もないので、来たい時に来れば良い、という気楽な場所なんです。
コミュニティにうまく馴染めなかった子どもたちは、子ども食堂を通じて他の世界にも触れることで、気持ちや見方を変えられるきっかけにもなります。
毎回、何人くらい集まりますか?
だいたい40人前後は集まります。
ただしコロナ禍になってからは、お弁当やオムツ、ミルクなどの子育て物資を、企業から寄付していただき、配布するような活動をしています。
何名くらいで運営されているのでしょうか?なかなか大変ですよね。
毎回スタッフは5〜6人くらいですね。
子ども食堂自体は夕方からですが、朝から買い出しに行ったり、準備をしたりするので、ほぼ1日かかります。
月に何度くらい実施されていますか?
月に1度です。
私としてはもっとやりたい気持ちはあるんですが、今の体制ではなんとか月1回実施しているという感じです。
ただ、他にも同じように月1回実施できるところが、同じ地域にあと3ヵ所増えれば、毎週どこかの子ども食堂に行くことができる、という環境になるので、もっと子ども食堂が増えてくれるといいなと思います。
共働き世帯が増えて重要性が高まっている「学童保育」での取り組み
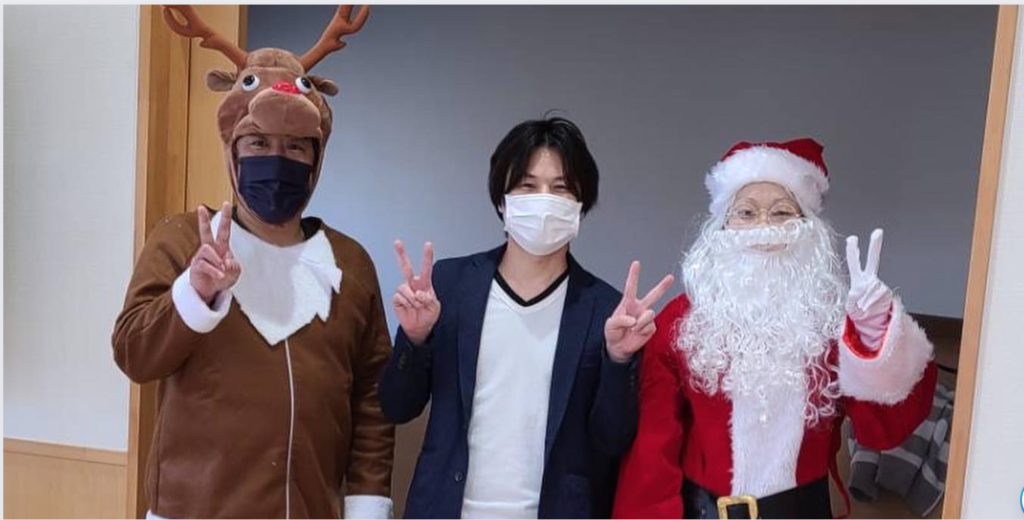
学童保育とはどんな活動ですか?
平日の学校が終わった後から、保護者の仕事が終わるまでの時間に行く場所です。
児童が一緒に遊んだり、宿題をしたりしています。
最近は共働きの家庭が多いので、学校が終わってから、預かってもらえる場所が必要なんです。
1日のスケジュールは決まっていますか?
だいたい決まっています。
勉強する時間、外で遊ぶ時間、自由時間など、流れに沿って運営しています。
スケジュールを決めていた方が、支援員さんが子どもたちを危険から守りやすくなりますし、心豊かに時間を過ごしてもらえると思うんです。
子どもが安心できる場所にするためには、どのような工夫が必要だと思いますか?
やっぱり話し方や接し方が大切ですよね。
支援員さんの対応一つで、感じ方が変わるため、子どもへの接し方には気をつけています。
今の子どもたちが何を求めているのか?」と考え続けて今の活動がある

子どもの居場所を作る活動を幅広くされている印象がありますが、最初はどのようなことから始めましたか?
活動を始める前は、今の子どもたちが何を求めているのか?
どうすれば居場所を作ってあげられるのか?がわからなかったんです。
そのため、大分県内で開かれている、子育て関連の講演会への参加や、実際に活動をされている施設の館長へ会いに行き、とにかく話をお聞きしました。
そうすると、少しずつ私に合う活動の形が見えるようになり、まず始めたのが「子ども食堂」でした。
実際に子ども食堂を始めると決めてからも、お金・場所・人の問題などを、一つずつクリアしていくのが大変でした。
お金、場所、人の課題はどうやってクリアしましたか?
私が子ども食堂を始めたのが今から5年前でした。
今でこそ子ども食堂は広く認知されています。
当時は「何それ?」という状態だったので、とにかく1人ずつに説明して、理解してもらい、協力してくれる人を増やしていきました。
お金に関しては、クラウドファウンディングを実施して、多くの方々に支援していただいたおかげで、なんとかスタートできたんです。
〈取材・執筆=林 勇士〉
中村さんは別府市市議会議員に挑戦します!
今回インタビューにご協力いただいた中村さんは、2023年4月23日が投票日の「別府市市議会議員選挙」に出馬されます。
今の別府市には、現役で子育てをしている議員がいない。だからこそ、自分が議員になって、別府市を「子育てがしやすい街」にするんだと、お話しされていました。
最近は「自分1人が選挙に行っても世の中は変わらない」と諦めている方が増えているようですが、選挙をきっかけに「どんな街だと自分や家族が住みやすい?」と考えてみてはいかがでしょうか?
まずは「無関心」から「考えてみる」というアクションに変えることから始めてみませんか?


